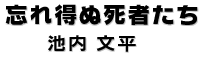
(1) やはり路上から始めるしかないだろう。 かつて、ぼくも参加している山谷制作上映委員会は『地熱の街から』と題する連続上映会(むろん、映画『山谷(やま)――やられたらやりかえせ』の)を何回か続けたことがある。この「地熱」というコトバは、ほかならぬ山岡強一がある文章のなかで使ったものだ。 「今山谷は、冬将軍を迎え撃つ熱い闘い=玉姫公園での越年闘争を終えたばかりだ。そして、地下タビを通して沁みる寒さを冬の弱い日溜まりに避けながら仕事を待つ山谷は、深い悲しみと強い怒りの喪に服している。そこに佇んだり、座り込んだりする〈時〉はない。この街の腐敗は、今にも、凍てつく舗道を突き破って噴出する予兆に膨れ切っているのだから……。昨年12月22日、佐藤満夫氏を殺した暴虐の膿は、冬の短い影に身を潜め、一切の纂奪を窺っている」 そう。映画監督・佐藤満夫は1984年の12月22日に、ヤクザ金町一家西戸組の組員・筒井栄一によって背後から刺され、山野の路上に斃れた。「――寒く長い山谷の冬の現実、しかしそこに決して凍結させられることのない地熱がある。そこを、佐藤さんは疾駆したのだ」「地熱の街」を佐藤満夫は疾駆し、そしてその地熱を孕んだ路上に斃れた。その〈時〉からすでに13年。ぼくたちはそこに佇んでいたのだろうか? あるいはただ座り込んでいただけだろうか? いや、たしかにぼくは日溜まりのなかで座り込んだり、ただ佇んでいるだけのことが好きなのだけど、そのぼくの、路上にうつった短い影を蹴とばすように、たくさんのひとが佐藤満夫の倒れ込んだアスファルトの上を通り過ぎていった。
現実にはただ冷たいだけのその地肌に、それでも、佐藤がそうだったように、真底からわき上がる地熱を感じとり、ある一瞬を共有した者たち。記憶されなければならないその者たち。その名前。 佐藤満夫刺殺後1年。同じ一家のヤクザに新宿路上で射殺された山岡強一。品川の運河に浮かんだアイヌ・酒井衛。山谷からアフガニスタンへ飛び、その地で散った写真家・南条直子。山谷最大のドヤ「パレス」の階段下で「野たれ死」んだプロレタリアート・梅本巧光。山谷労働会館が最後の作品となった建築家・宮内康。全世界の被抑圧民衆との地下水脈をさぐり、力尽きた池田修。そしていまでもその音色がぼくの頭の中で響いているサックス奏者・篠田昌已。人生を見事に下放した高木淳。走る靴音とともに姿をあらわし、バイクの音とともに消え去った見津毅――。 佐藤満夫を含むこの10人は、もう「この世」にはいない。再会は果たされないのだ。けれどもベンヤミンふうに言うなら、この人たちは「過去」にいるのではなく、すでに「未来」に属している。そこから目をこちらに向け、生きているこのぼくたちの現在を見渡しているに違いないのだ。 |
|
(2)
佐藤満夫。1947年生まれ。 いやおうなく全共闘世代。佐藤を知る者は彼を性急な性格という。ぼくもそう思う。全共闘から斎藤龍鳳に惹かれて映画屋稼業へ。いかにも無頼なニオイがする。事実、新宿あたりの呑み屋での武勇伝もそうとうにあったらしい。しかし無頼派は概ね心優しく心配りが細やかだ。麻雀でボロ負けしている相手にわざと振り込んだり…。ぼくが預かったガサブツをひき取りに来るとき、わざわざタクシーを酒屋にまわして「玄海・むぎ」一升をぶら下げてきたりもした。いや、そんなことはどうでもいい。 問題は山谷の映画に取り組んだときだ。ほぼ1年間、「支援」として山谷にかかわった佐藤は山谷の映画を撮ることを決意する。なにしろ寄せ場は磁力が強いのだ。表現を身体的に発想するものは必ずそこに引き寄せられる。寄せ場は「純粋な」労働力だけを寄せ集めるところでもないのだ。佐藤が何の契機で山谷の支援を始めたかは知らないが、それを映画に撮りたくなったという気持ちはよくわかる。支援から「共闘」への転換といってもいいだろう。ともかく佐藤は山谷を映画にすることを決意した。 「…この映画に取組むことによって、十五年続けた稼業の垢を洗い落し、生まれ変わりたいわけです」――(ぼくらにとって)有名な『映画で腹は膨れないが敵への憎悪をかきたてることはできる』(佐藤が山谷の仲間たちに映画について訴えるために用意した文章)のなかの、これも(ぼくらにとって)有名な一節である。他の部分はわりかた無頼っぽいというかダチ公の語り口で書かれているこの文章のなかで、この一節だけがご覧にように切ない真情の告白となっている。おそらくここに佐藤満夫の真面目がある。佐藤は15年目にしてはじめて「生まれ変わりたい」と思ったわけではなく、15年間ずっとそう思い続けていたのだ。 その15年前、1969年。東大闘争。佐藤は占拠した列品館でタイホされている。15年の垢とは決して「稼業」の垢だけではなかった筈だ。全共闘が素敵だったわけではなく、その後の15年間が愚劣すぎたのだ。その「垢」。 ――インサート・ショット/ある友人に佐藤は告げた。獄中の政治犯(東アジア反日武装戦線の兵士)の奪還のために、このクニの苗字のない一族のナンバー・2(当時)をナントカ、スルと。およそ実行不能な「計画」ではあったが、それでも100%ダメというわけでもなかったろう。実に惜しい。/ それから15年後、1999年。佐藤の不在のあいだのこの15年はもっとグレツになっている。 結局、佐藤は映画を完成できなかった。薄曇りの早朝に刺し殺されたからだ。山谷の映画を撮りはじめるということはそれほど罪深いことなのか? けれども佐藤満夫は1本の映画を完成させる意志を遺していった。自らのドテッパラに突き刺さった柳刃包丁を闇の中へ、ちょうどリレーのバトンをさし渡すかのようにして。1984年12月22日、死去。 |
|
(3)
山岡強一。1940年生まれ。 山さん――そうみんなが呼んでいた。初対面のひともつい「山さん」と呼ぶような親密さにあふれた人柄。 あの日、路上に倒れ込んだ佐藤満夫は「追え!」と言った。自分をいま背後から刺し、血のついた刃物を握ったまま逃げ去った男を「追え!」と言ったのだ。それが佐藤の最後のコトバだった。 山さんはそのコトバを忠実に守った。その後の自分の人生の最後の1年間を通して佐藤満夫との簡潔な「約束」を果たしてみせた。山さんは佐藤から映画を受け継ぎ、それを見事に完成させたのだ。 佐藤を殺した虐殺者の裁判では(たった3回の公判!)、その男の「単独犯行」とされた。だが映画ではその男に命令を下したヤクザ組織の指令系統がはっきりと写されている。そしてそのうえで、山さんは、それを可能としたこのクニの実相を誰の目にも明らかなように暴きだしている。 山さんは、この映画の現場にたち至る前に船本洲治の遺稿集の編集に携っていた。船本洲治は1975年に沖縄・カデナ基地前で焼身自殺した寄せ場の闘士であり、その行動と思想は現在に至るまで寄せ場の運動に大きな影響を残している男だ。山さんの完成させた『山谷(やま)―やられたらやりかえせ』にも当然その思想は盛り込まれている。 この映画が初公開された直後、山さんは「佐藤さんのながい喪がやっと明けた」と語った。また、「船本のことはもう言わないことにしよう」とも語ったという。それはむろん訣別のコトバではない。自分のやるべきことをはっきりと見定め、背負うべきものを一切合財ひきうけた者が、そこより更に一歩まえに出ようとする決意を込めた静かなコトバに違いない。 船本の遺稿集と佐藤からひき継いだ映画。この二つをつくりあげた山さんは、次にどこへ足を踏み入れようとしていたのだろう。――おそらく、それは「日雇全協」だ。 全協自体は、四大寄せ場(大阪・釜ヶ崎、名古屋・笹島、横浜・寿町、東京・山谷)の運動を基盤に、山さんたちが尽力して1982年に結成された労働運動体だ。けれども山さんは数年を経た全協の運動体にかなりの不満を抱いていた。佐藤満夫を目の前で殺された後になお「現場主義」に汲々とする全協の現状を激しく批判もしていた。 やはり映画は、山さんにとってひとつの「武器」だった。その映画を上映することで全国を「席巻」し、新たな、山さんの考える全協運動を始めようとしていたに違いない。それはひとり寄せ場―日雇労働者だけの運動ではない。日々、尊厳を殺ぎ落とされ、生命まるごとを使い捨てられている人びとすべてと繋がってゆこうとするものであっただろう。その「日雇全協」に山さんは戻ろうとしていた。 ある時、友人と酒を飲んだ帰りに、山さんは新宿副都心にそびえる高層ビル群を指さし、こう言ったという。「ねぇ、見てごらん。あれが敵だよ。強大でしょ」。映画が完成して半月後、山さんは、国粋会金町一家金竜組・保科勉の放ったピストルの弾丸によって、新宿の路上に無言で崩れた。 ――その10年後、1996年に友人たちの手によって、映画と同じタイトルの遺稿集『山谷(やま)・やられたらやりかえせ』が刊行された。映画は、さまざまな曲折を経ながらも、現在も上映し続けられている。1986年1月13日、死去。 |
|
(4)
酒井衛。1943年生まれ。
酒井衛が亡くなって3年目に上梓された追悼集『イフンケ』に萱野茂さんが初対面のときのことを書いている。 《ある日のこと、めんこい嫁さんを連れてやって来た。その嫁さんに車を運転させて、それが、酒井さんとの最初の出会いです。「おおー、あんた、どこのアイヌだ? いい顔してるなー、二風谷アイヌでそういう、いい顔のアイヌいないぞ」と言うと「ああ、そうかい、俺、十勝のアイヌだ」と、さも嬉しそうに言っていた顔を思い出します》 「ザ・アイヌ」あるいは「大アイヌ」とも呼ばれていたらしい。最もアイヌらしいアイヌということだろう。たしかに、山谷にはたくさんのアイヌがいるが、酒井衛はひときわ光っていた。 それはなにも「カオ・カタチ」だけのことではない。いまではすでに「伝説化」されているが、酒井衛の山谷登場のシーンが強烈だ。――1973年、越年・越冬闘争さなかの山谷・玉姫公園。そこには被抑圧民族・アイヌとの連帯を謳う現闘委(山谷悪質業者追放現場闘争委員会)のタテカンが立っており、その中に「……滅びゆくアイヌ」という字句が書かれていた。暖をとるための焚火が並んでいる。酒井衛はその煙をまとうようにして灰の中からむっくりと起き上がり、「アイヌは滅んでいない! アイヌはここにいる」と言ったというのだ。 酒井衛はそれ以前からも、そしてそれ以降もずっとアイヌだった。『イフンケ』の目次から拾ってみよう。コタンに生まれて―北海道時代/アイヌは滅びていない―山谷時代/カムイワッカ―アイヌ解放研究会時代/やられ続けてたまるか―東京へ・死まで――そのかん現闘委をはじめ山谷統一労組、アイヌ革命委員会(フラクション)、赤軍派(プロ革)、山谷争議団(全協)、アイヌ解放研…と、酒井は全身で進んできた。最も暑い磁場の中で求心的な前衛組織と民族解放という普遍性、そして下層の実力闘争を追求し、そのまっただなかで生きてきた。酒井衛は存在そのもの自体が反帝国主義であった。 1987年7月、酒井は新宿駅構内の交番の中で暴行をうける。職質していた警官が席をはずした間に、見知らぬ男が入ってきて酒井を殴りつけるという信じ難いことが実際におこった。警察は自分らで救急車を呼び酒井を病院に運んだくせに、そのような事実はないとシラバッくれ、立ちあった警官を弁護士にも会わせようとしなかった。酒井は右脚骨折の重傷を負った。 そして「天皇Xデー」が公然といわれていた88年(天皇はその年の9月に「下血」)4月15日、酒井は品川区の京浜運河に浮かんでいるところを釣船に発見された。死因は「溺死」だが、これも検視官などの証言がバラバラで、真相はいまひとつはっきりしない。 |


